拠点から離れていても、リアルタイムで現場作業員へのリモート支援を実現。防塵防水、防爆、酷寒の-20°Cから+50°Cの高温作業場まで、あらゆる環境下での活躍を可能に。RealWearは、どんな場所でも作業を支える、あなたのナビゲーターになります。
産業用スマートグラス「RealWear」のご紹介

産業現場に特化したスマートグラスRealWear(リアルウェア)は、ハンズフリーで音声コマンド操作できるスマートグラス。軽量で頑丈なボディと高速で安定した通信が、あらゆる業種の現場作業員を支援します。
製品情報




1990年、株式会社東芝に入社後、SCM・ERP・CRM・インダストリアルIoTなどのソリューション事業に従事していました。現在は合同会社アルファコンパスの代表CEOを務め、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)やマーケティング支援に注力しています。また、中小企業診断士としても活動し、講演や執筆を通じて製造業の変革を推進しています。
RealWearの第一印象は?
━━ RealWearの「Navigator520」になります。どうぞ手に取ってみてください。
福本:ものすごく軽いですね!
━━ 他のスマートグラスと比べてどうでしょうか?
福本:ハノーバーメッセ*などの展示会で体験をすると、重量的に長時間使用するには厳しいと思われるようなスマートグラスもありましたが、これ(RealWear)なら軽いので長時間利用にも耐えられそうですね。

━━ 第一印象として、どのように使えそうだと思いますか?
福本:マニュアルを見ながら作業を行ったり、カメラからの現場映像を遠隔の人に共有して、相互確認と情報共有をしながら作業を進めるといった使い方が考えられると思います。
━━ 活用方法にはどのようなものがあると考えられますか?
福本:スマートグラスの活用方法は大まかに2つあると考えています。1つはインダストリアル・メタバースのようなソリューションの活用において、現実空間を再現したバーチャル空間上で、モノの確認などを行いながらコミュニケーションを取るという活用。もう1つは、現実空間において、マニュアル確認や遠隔からの支援などの情報を参照しながら作業を進めていくような活用だと思います。このRealWearは現実空間とバーチャル空間を重ね合わせる事で、その両方を同時に体験する、いわゆるMR(Mixed Reality:複合現実)タイプのスマートグラスではないと思うので、後者の活用用途が向いていると思います。
━━ 確かに、メタバースなどで使われているスマートグラスでは、また用途が変わってきますよね。
福本:没入感の高いタイプのスマートグラスだと、足元に危険があるような現場では活用リスクがあるのではないかと思います。あとは、手が油まみれになるような現場だとタブレットなども使えないので、このような形で作業しながら音声操作もできるというのは、メリットも大きく、現場作業に適したスマートグラスなのではないかと思います。

課題は「匠の技術の伝承」
━━ 具体的な活用方法は、どのようなものが考えられますか?
福本:匠の技術の伝承などでしょうか。今後、日本では少子高齢化が進み、匠の数も減少していきます。また、人間である以上、歳とともに身体能力は落ちていってしまいます。例えば、現在、ベテランのノウハウに頼っている社会インフラのメンテナンスにおいては、ベテランの方が高所でメンテナンス作業を行うようなケースもあり得ます。危険度も高く、1日に行うことができる作業量も限定されているといった課題もあると思います。
━━ RealWearはまさに人手不足に対するソリューションとして打ち出していますね。
福本:従来は、現場で匠の技術を人から人に時間をかけて技術伝承をしていくような取り組みも多く、たとえば「いま、音が変わっただろう」などと伝え、その時に行うべきことを実地で教えたりするようなケースもあります。これだとやはり育成に5年、10年かかってしまいますよね。
━━ 伝統工芸の伝承みたいになっているんですね。
福本:そうですね。でも、こういったものを活用すればOJTしながら映像や音声を記録し、見返した時に「あ、確かに音が変わったな」と気づけるかもしれないですよね。

━━ 作業風景を現場視点で残せるのは、スマートグラスの大きな特徴ですよね。
福本:また、このスマートグラスを装着していれば、通常は現場から報告が上がらない「あ、ヤバい」などと言った音声も記録できるのではないでしょうか。
━━ ヒヤリも記録できるってことですね。
福本:そうですね。ヒヤリの記録も結構大事だと思います。「何がヤバかったんですか?」と聞き返せますよね(笑)。人である以上、意図的かどうかに関わらずミスは起こり得ます。作業をすべて自動化できればいいのですが、そうはいかない場合も多い。なので、こうしたデバイスを用いてトレーサビリティを確保できる点に対するニーズもあるのではないでしょうか。
━━ トレーサビリティに関連して、当社でもデジタル・トルクレンチとRealWearを連動させたサービス*を提供中です。
福本:作業実績収集や作業ミスの削減を支援する仕組みも必要ですよね。
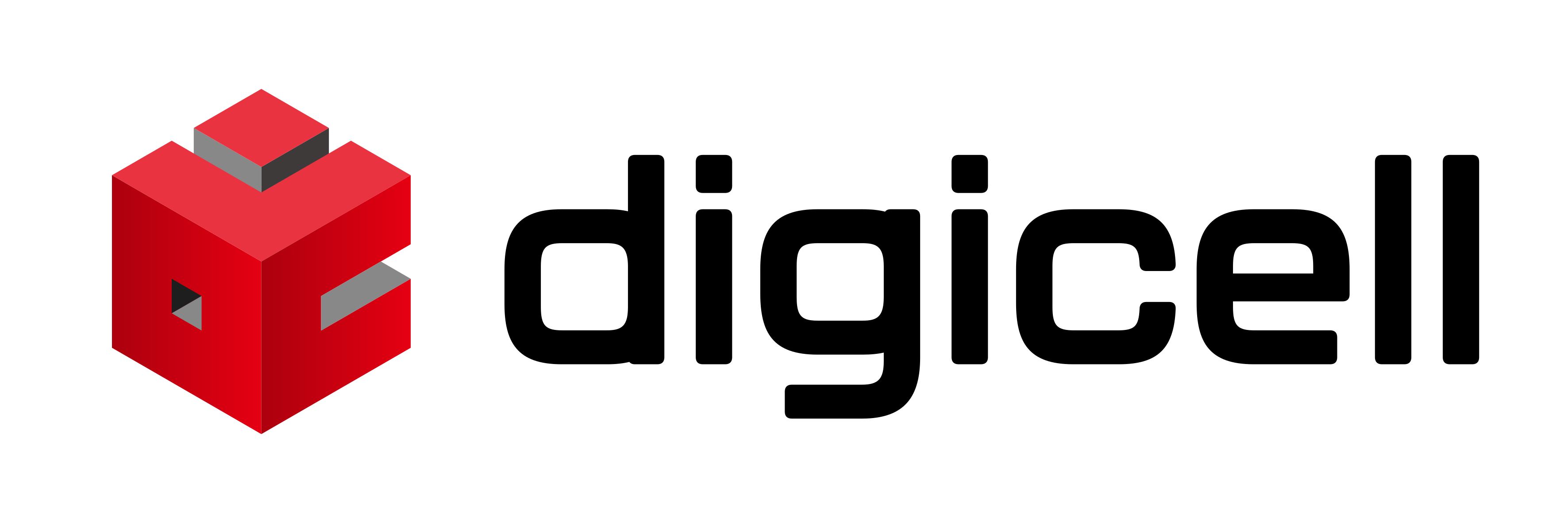
━━ こうしたトレーサビリティに関するサービスは、ハノーバーメッセでも紹介されていましたか?
福本:例えば、生成AIを使ったショーケースで、作業者の手元に設置されたカメラ映像に基づき、AIが「手に取った部品が間違っている」といった指摘してくれるものなどがありました。他にもネジ締め時のトルクなどの作業履歴が自動で記録されるようなショーケースも展示されていました。
━━ スマートグラスなら作業者目線での記録ができるので可能性が広がりそうですね。生成AIのショーケースは他にも紹介されていましたか?
福本:ええ、出ていました。2025年はもっと増えると思いますよ。
生成AIとの連携
━━ 生成AIと連携させた活用方法は、他にどのようなものがあると思いますか?
福本:例えば、複数言語への動的翻訳なども便利だと思います。英語のドキュメントしかなくても、日本語など他の言語に動的に翻訳してくれるのは、メリットが大きいですよね。
━━ 言語の課題は製造業でも多いのでしょうか?
福本:欧州などにおいては言語状況が多様なので課題だと思います。日本の場合、日本語ベースでのやりとりが中心なのでそこまで苦労していないと思うのですが、海外とのやりとりや海外展開が増えていけば多言語対応も必要になっていくと思います。
━━ 言語を問わずに動的翻訳できるのが、生成AIの強みですね。現在当社でも生成AIとRealWearを組み合わせたドキュメント生成サービスを開発中でして、ここに動的翻訳機能も付けられたら良さそうですね。
福本:レポート作成の際に生成AIの支援を受けるという使い方は良い用途だと思います。例えば、保守作業のメモ記録に特定の機械部品の単語しか書かれていないようなケースも現実にはあったりします。そうすると、その時に何の障害があって、どんな対応をしたのかを振り返りたくても、分からないと思います。欠けた情報を後から補うことは難しいので、作成時に情報が不足していることをAIが指摘してくれサービスなども大事だと思います。それに、AIならマルチコンテキストの情報を収集、活用できますからね。
━━ 確かに、AIであれば、文字情報だけでなく、映像なども併せて作業の完了判断が可能になりますね。
福本:将来的には、複数人で作業をしているときに、あちらの作業者はこれをやった、こちらの作業者ではこれをやったと、トータルで全部の作業が終わったのかAIが判断してくれるようになると、活用も進むと思いますね。
━━ 作業報告を個別で行うのではなく、複数人のトータル情報で判断できたら便利ということですね。
福本:そうですね。ただ、RealWearに色々なソリューションを組み合わせる必要も出てくると思います。
━━ 他に、生成AIを使って、もっと面白いんじゃないかと思うような使い方はありますか?
福本:前々から思っているのは、生成AIでレポートが作れるなら、マニュアルも作成できるだろうということです。
━━ マニュアルに関する課題は確かに聞きますね。
福本:文字情報だけで、全ての作業内容をインプットするのは難しい気がします。オペレーション作業を文字だけで表現するのには限界がある気がします。「異常時に〇〇スイッチを押してください」と書かれていても、ボタンが沢山あって、どれがそのボタンなのかが、一目で判別できなかったり、場合によってはそのボタンがどれかということまでドキュメントを見て調べなければいけないようなケースもあるのではないでしょうか。視覚化することで分かりやすくなるようなケースもあると思います。
━━ マニュアルを作ってはいるけれど、現場ではまったく使われていないというケースもよく聞きますね。
福本:多いと思いますよ。なので、AIを使って映像や音声情報を基に視覚的なマニュアルを自動生成できたら、活用が進むと思いますね。

今後の展望は?
━━ コロナ禍も終わって、遠隔支援の需要が少し落ち着いてきているんですが、今後の需要はどうなっていくと思われますか?
福本:これからも増えていくと思いますよ。
━━ それはなぜでしょうか?
福本:匠の数が減っていくからですね。例えば、今までなら10か所の全拠点に配置できていた匠が、5人まで減った場合、残りの5箇所は遠隔支援などで補う必要がでてきますよね。そうした時に遠隔支援での対応ニーズが出てくると思います。人の育成に時間がかかっていることもその背景にあると思います。
━━ やはり冒頭でもおっしゃっていた「匠の技術の伝承」が課題なんですね。そうした中、文字情報だけでなく映像や音声データも記録することができ、AI連携も可能なスマートグラス、とりわけ現場向けであるRealWearなら活躍できると再確認できました。
終わりに
今回、合同会社アルファコンパスの代表CEO福本勲さんにお話を伺い、実際の製造現場でどのように活用できるか、その具体的な活用方法をお聞きしました。今一度、RealWearのポイントをおさらいします。
軽量さとフリーハンド操作で
作業を妨げない
作業効率を落とすことなく、軽やかに操作を行えます。

作業者目線で
映像・音声データが記録可能
リアルタイムでの状況把握と共有が容易になります。

現場レベルで行える
生成AIでの効率化
最新のAI技術を活用し、現場業務を最大限サポートします。

NSWはお客様が抱える課題の解決に向け、 スマートグラスの提供だけでなく、豊富な導入実績をもとにした包括的なソリューションもご提案します。ぜひ、実際に導入いただいたお客様の声もご覧ください。





